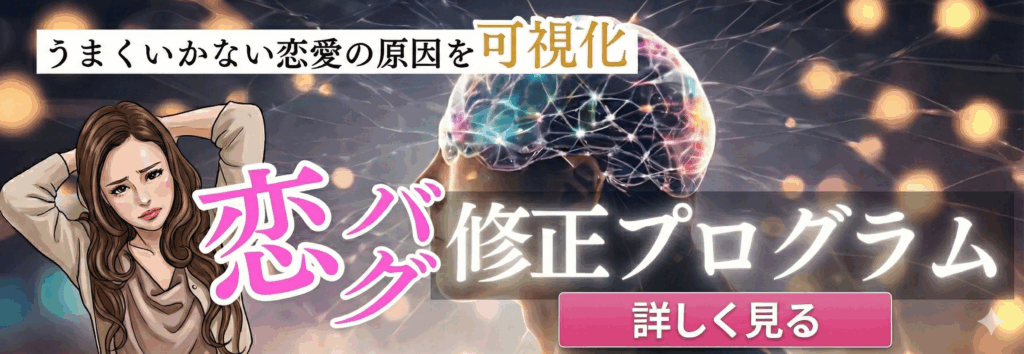お盆って2回あるの?やるべきこと、やってはいけないこと
お盆とは、亡くなったご先祖様の霊をお迎えし、供養する大切な期間です。
ご先祖様がこの世に戻ってくるとされるこの時期には、精霊棚や提灯、精霊馬などさまざまなお飾りでおもてなしをします。
しかし「なぜお盆は7月と8月の2回あるの?」「何をすればいいの?」「NGなことってあるの?」など今さら聞けない疑問ってないでしょうか?
こうした疑問が浮かぶのは、ご先祖様を大切に想う気持ちの表れですよね。ただ、毎年お盆を迎える中で「心を込めてはいるけれど、このやり方で本当に供養になっているのかな?」と、ふと不安がよぎることはありませんか?
実は、良かれと思って続けていることが、本当に届く供養になっていないケースは少なくありません。
本題に入る前に、少しだけ、まさにそのご経験をされたクライアント様の動画をご覧ください。
「自分では供養しているつもりだった」という、水子供養に関する大変貴重な実体験です。
▼ 【水子供養】自分なりに供養はしているつもりだった 水子成仏供養のご感想①
▼ 成仏していないのに供養できるわけがない 水子成仏供養のご感想③
いかがでしたでしょうか。想いを正しく形にすることの大切さを感じていただけたかと思います。
それでは、ここからは皆様が安心してご先祖様をお迎えできるよう、「お盆のやるべきこと」について一つひとつ解説していきます。
なぜお盆は「7月」と「8月」の2回あるの?
仏教の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」に由来
お盆は、仏教の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」に由来すると言われています。
この由来は『仏説盂蘭盆経』に記されています。
釈迦の弟子である目連尊者(もくれんそんじゃ)が神通力で餓鬼道に落ちた亡き母を見つけ、釈尊に救い方を聞きました。
釈尊は「7月15日にごちそうを用意し、僧侶たちに供養することで、母を救える」と説き、それを目連尊者が実行したところ、母は成仏できたといわれています。これが盂蘭盆会、そして現代のお盆のルーツだと言われています。
7月のお盆(新盆・東京盆)
東京や一部の地域では、月遅れではなく本来の旧暦に近い7月13日〜16日にお盆を行います。これが「新盆」または「東京盆」とも呼ばれる由来です。
8月のお盆(旧盆・月遅れ盆)
多くの地域では、農繁期や梅雨明けを避けるため、旧暦に近い8月13日〜16日にお盆を行います。これを「月遅れ盆」と呼びます。
このように2回行うというのではなく、地域や宗派・家庭によって時期や風習などが異なります。
総務省統計局による「社会生活基本調査」でも、地域によりお盆の時期が異なることが確認されています。

カウンセラー
捺月美羽
ちなみに、美羽の秘書さんも「自分の地元では8月だけれど、旦那の家はお盆が7月らしい」ということで、結婚後に戸惑った経験もあったそうよ?
大丈夫か不安な時は、自分の住んでいる(もしくはこれから住む)土地の風習を年長者や家族に確認しておくと安心。
お盆の時期は地域によって異なり、東京や一部都市では7月、全国的には8月に行われることが多くなっています。
これは、旧暦・新暦の違いや農作業の繁忙期を避けた調整によるものです。
→ 出典:六白亭|お盆とは?
お盆飾りの意味と正しい準備方法
お盆はご先祖様が快くこの世に戻れるように、祭壇や飾りでお迎えするのが習わしです。ただ、意外と意味を知らずにいる人も多いのではないでしょうか?主な飾りと意味を簡潔にご紹介します。 精霊馬(しょうりょううま)はキュウリを馬、ナスを牛に見立て、ご先祖様が早く来て、ゆっくり帰るという意味が込められています。
提灯や精霊棚、水の子などの飾りにも一つひとつ意味があり、形だけでなく“心で迎える”ことが大切です。
盆棚(ぼんだな)・精霊棚(しょうりょうだな)
ご先祖様の居場所になる祭壇です。場所は仏間、床の間、縁側、仏壇前などに設置します。真菰(まこも)やゴザを敷き、お位牌を中央に安置します。
飾るものの例:
- 精霊馬(ナスとキュウリ)
- 故人の好物(果物や甘味)
- 精進料理
- そうめん、だんご
- 季節の野菜
盆提灯(ぼんちょうちん)
玄関や仏壇の横に飾る灯り。ご先祖様が迷わず帰って来られるよう、道しるべの役割を果たします。
新盆の際は「白提灯」を用意し、初めて帰ってくる霊を特別に迎えます。
精霊馬(しょうりょううま)
キュウリは馬、ナスは牛に見立て、割り箸で脚をつけます。ご先祖様が馬で早く来て、牛でゆっくり戻るという意味があります。
ほおずき
赤い実が提灯に似ていることから、道しるべとして飾られます。生花と一緒に束ねたり、単体で飾ったりします。
まこも(真菰)・蓮の花
まこもは邪気払い、浄化の意味を持ち、棚に敷いて使います。蓮の花は仏教における神聖な存在で、お盆の飾りにも最適です。
水の子・閼伽水(あかみず)
刻んだナスやキュウリ、洗米を蓮の葉にのせた「水の子」は、無縁仏の供養に使います。閼伽水は、仏前に供える清らかな水のこと。
麻がら(おがら)
迎え火・送り火の際に焚くアイテム。麻の茎を乾燥させたもので、故人が迷わず帰れるように灯します。

お盆にやるべき主なこと 【保存版】
お盆飾りの準備(精霊棚や提灯など)
- 時期:7月または8月の13日までに(当日バタバタしないよう、お盆月に入ったタイミングで準備を進め、初日に間に合うようにしましょう)。
- 仏壇や精霊棚(盆棚)を整え、真菰のゴザ、精霊馬、供物(そうめん・果物・精進料理・だんごなど)を飾ります。
- 盆提灯を灯し、ご先祖様の帰る道を照らします。
- お盆に用意する 盆棚(精霊棚) は、ご先祖の霊が帰ってくる場所として設けられる祭壇で、位牌やお供え物などを整えて飾ります。
- 多くは2段〜3段の構成で、上段には位牌、中段に霊供膳や果物、最下段に精霊馬や水の子などを並べます。真菰(まこも)を敷き、四隅に竹を立てて真菰縄を張るのが伝統的な形式です。
参考:写真付きでの具体的なイメージはこちら:All About「盆棚・精霊棚の作り方」
迎え火を焚く(13日)
- ご先祖様の霊を自宅へ迎えるため、玄関や門前で迎え火を焚きます。
- 一般的には「麻がら」を素焼きの皿(ほうろく)で燃やします。
- 迎え火や送り火はご先祖様を導くための儀式ですが、近年では住宅事情や火災予防の観点から、提灯やLED電灯を代替的に用いる家庭も増えています。
ご先祖様を供養する
- 仏壇や精霊棚の前で朝晩にお線香をあげ、お参りします。
- 家族そろって手を合わせたり、故人の思い出話をしたりするのも供養になります。
お墓参りをする
- お墓の掃除をし、花や線香を供え、ご先祖様に感謝を伝えます。
- 時期は地域差がありますが、13日〜15日頃に行うのが一般的です。
精進料理を供える、いただく
- ご先祖様が好んだもの、旬の野菜、精進料理などをお供えします。
(お供えした後は、家族で感謝していただくのが供養になります)
無縁仏にも気を配る
- 水の子(刻んだ野菜+洗米)や閼伽水を用意し、縁のない霊への供養も忘れずに。
- 「古くから『無縁仏を供養すると、家に迷い込まずに済む』という言い伝えが一部地域に残っています。」
送り火を焚く(16日)
- ご先祖様をあの世へ送り出すために送り火を焚きます。
- 迎え火と同様に、門や玄関先で麻がらを燃やします。
- 迎え火や送り火はご先祖様を導くための儀式ですが、近年では住宅事情や火災予防の観点から、提灯やLED電灯を代替的に用いる家庭も増えています。
飾りの片付け・処分
- お盆が終わったら、精霊棚や飾りを片付けます(16日の「送り火」終了後〜17日中)。
- 生花や精霊馬は、お寺でお焚き上げをお願いするか、塩で清めて処分します。
- 盆提灯や棚などは来年用に丁寧に保管します(ただし白提灯は新盆用なので供養後処分)。
※片付けが遅れてしまう場合は、塩で清めた半紙で包むなどして丁寧に扱いましょう。
お盆にやるべきことまとめ(チェックリスト)
項目 | 実施日 or タイミング |
| お盆飾りの準備 | 13日まで(余裕をもって準備) |
| 精霊馬・供物を用意 | 13日まで |
| 迎え火を焚く | 13日夕方 |
| お墓参り | 13日〜15日 |
| 仏壇へのお参り | 毎日(朝夕) |
| 水の子・閼伽水の用意 | 初日まで |
| 精進料理を供える | 毎日 or 1〜2回 |
| 送り火を焚く | 16日夕方 |
| 飾りの片付け・処分 | 16日夜〜17日 |
お盆にやってはいけないこと&注意点
お盆はご先祖様を敬う時期。以下のようなことは、できる限り避けましょう。
殺生を連想させる食べ物を避ける
肉や魚などの殺生に関わる食材、辛い物やにおいの強い物(ニンニク・ネギなど)は控えましょう。代わりに精進料理や野菜、果物などを供えます。
トゲのある花・香りの強い花は避ける
バラやユリなどトゲや香りが強い花は、仏花にはふさわしくありません。菊やリンドウなど、落ち着いた花を選びましょう。
これらは仏教の精進潔斎・供花の基本マナーに基づくものです。
供物を粗末に扱わない
お供えした果物や菓子類は、家族でありがたくいただくのが供養の一環です。捨てたり放置したりしないように気をつけましょう。
心をこめたお盆の準備で、つながるご縁
お盆は、ご先祖様と向き合い、心をつなぐ大切な行事です。飾りひとつひとつに意味があり、その背景を知ることでより深い供養ができるかもしれません。
今年のお盆は時期や作法を確認しながら、心をこめて準備してみませんか?
華やかで温かなおもてなしが、ご先祖様への感謝と安らぎを届けてくれるはずよ^^
※地域の慣習により内容が異なる場合があります。あくまで一般的な風習を参考にしてください。
お盆時期のお悩みのご相談も多く...
遠くて帰ることが困難、事情がありお墓に行く事が出来ないなど様々ですね。
特にコロナ禍以降、帰省が難しい人に向けた遠隔供養の希望も多くなっています。
私も、先祖を大事に思う気持ちはとても大切なことだと思います。 その気持ちを叶えるべく今アンケートを実施しているので是非 ご協力くださいね。
供養の“気持ち”をどう届けたいですか?(アンケート)
ユタではない「ナカムチ」へ──なぜ私は沖縄の拝みにこだわるのか?
ご先祖様の尊い供養を心から行っていますか?
ヒーリングに関するご案内・免責事項
当サイトでご案内している各種ヒーリングは、宗教的・医療的な行為ではありません。
特定の宗教や信仰との関係は一切なく、心と氣のバランスを整え、
前向きに生きるためのサポートを目的として行っております。
ヒーリングによる効果・体感には個人差があり、
必ずしもすべての方に同じ結果が得られることを保証するものではありません。
現実の変化を促す“氣づき”や“心の整理”を目的としています。
お申し込みはご本人の自由意思によるものであり、
当方から強制・勧誘・恐怖を与えるような行為は一切行っておりません。
お申し込みをいただいた時点で、上記内容にご理解・ご同意いただいたものといたします。
(2025年10月 追記・全ヒーリングページに明確化しました)
なつきみう LINE登録
捺月美羽(なつきみう)LINE公式アカウントでは、一早く情報が流れます。
捺月美羽のカウンセリングや茶会ランチ会などは先行予約で満員になるのがほとんど。
先行予約や特別特典付き企画、毎月の無料ヒーリングのお申し込みや特別企画、割引クーポン情報は、ラインにて行いますので登録してチャンスを手に入れてくださいね。
お問い合わせ
下記フォームよりご連絡ください。
※男性の方からのご相談はお受けしておりません。